お正月、あなたはどう過ごしていますか?ゴロゴロこたつでみかんの寝正月。初日の出や初詣に行って願をかけ、おせちを食べますか。実は、おせちを食べることも「めでたさを重ねる」という意味で縁起をかついでいます。
「今年もいい年でありますように」毎年誰しもが、元旦にこう願うのではないでしょうか。年明けから好スタートを切りたいと思い、古くから1年のめぐり合わせを初夢で占うという風習があります。
縁起の良い初夢であれば、その1年が良い年に、縁起の悪い初夢の場合には、そのことを気にかけて1年を過ごすことで、災いを防ぐという大事な夢とされています。
良い初夢の内容とその意味は?良い夢を見る方法はコントロールできる!
縁起の良い夢として「一富士二鷹三茄子」はとても有名ですが、実はその続きがあることは知っていますか? 縁起の良い夢ベスト6とその由来をご紹介します。
「一富士二鷹三茄子」ことわざの由来とは
「一富士二鷹三茄子」このことわざは、江戸時代の初めころから言われるようになったようです。ではこのことわざは、どのような由来で縁起物とされるようになったのでしょうか。
由来には諸説あるのですが、大きく分けて三つあります。

価値の高いもの説
徳川家康が、自分の住んだ駿河国(現在の静岡県中央部)の価値の高いものを並べたとされる説です。日本一の標高の富士山、次に標高のある駿河の愛鷹山(あしたかやま)、そして初物の折戸茄子の値段とされています。
折戸茄子は、三保半島の折戸という地域で、黒い砂で栽培しているため、太陽光の吸収が良く、通常より1~2ヶ月早く収穫が出来ました。
「初物を食べると、七十五日長生きする」と言われた始めた江戸時代、どこよりも早く出回る折戸茄子は、とても人気があり大変貴重だったようです。
徳川家康の好物説
二つ目は、徳川家康の好物が富士山や鷹狩り、初物の折戸茄子であったという説です。富士山は神々が宿る霊山と言われ、その手前にある「三保」という島と海との景色が、「極楽浄土」に見えたそうです。
そして、鷹狩りと折戸茄子は徳川家康の大好きなもの。「初茄子値高く」と5個で一両したと言われたそうです。
一両というと、約10万円ほどしたのではないでしょうか!折戸茄子好きの家康には、500個献上された記録もあるそうです。
これだけ高価で貴重な初物だったら、確かに縁起もいいですよね。それにしても庶民には、手が届かない品!
天下を取った戦国武将、家康にあやかって、縁起物としたのかもしれませんね。
駒込の名物説
三つめは現在の東京、江戸に移動します。現在の文京区、駒込に富士山を信仰する駒込富士神社があります。「一富士」の富士山とはこの神社にある、富士塚のことを指しているようです。
富士塚とは、江戸から遠い富士山まで、なかなか行けない人達が、富士山に登った時と同じご利益を、ここで賜りたいと作ったものです。
そして、この近くには鷹匠(たかしょう)の屋敷があり、ここでは将軍が鷹狩りを行う際に使う、鷹を調教していたそうです。
現在、鷹匠屋敷跡には都立駒込病院が建っていて、ここの発掘調査では、鷹の餌や調教に使用したと思われる動物の骨が出土しているそうです。
駒込富士神社の裏一帯の畑では、とても良質な茄子がとれたそうです。
江戸時代に浮世絵師の歌川国芳が「江戸じまん名物くらべこま込のなす」を描いていて、「駒込茄子」がとても有名な名産品だったことを伝えています。
駒込富士神社の境内には、本駒込が「一富士二鷹三茄子」発祥の地だという解説板があるそうなので、お正月にこの地をぶらりとお散歩してみたら、もしかして縁起の良い夢が見られそうですよね。
「一富士二鷹三茄子」の続きがある?

お正月の初夢で見る縁起のいい夢として「一富士二鷹三茄子」ということわざが一般的ですが、これに続く縁起のいい夢は6番目まであります。
その続きは「四扇(しおうぎ)五煙草(ごたばこ)六座頭(ろくざとう)」です。これらはどんな意味を持っているのでしょうか?
初夢のことわざの意味は?
富士山や鷹が縁起がいいことは、なんとなくわかるけれど「茄子」や「煙草」は、何で?
まして、「座頭」ってよくわからないという人も多いと思います。一つ一つの意味を見てみましょう。
富士
日本一の高くてとても美しい山で、理想や高い目標を達成することや、末広がりで縁起がよく立身出世の象徴とされています。「富士」という言葉を「不死」「無事」とかけて、1年の健康を意味しているとも言われています。
鷹
鷹は、強く高く羽ばたいて大空を舞っていることから、開運につながると言われています。また、鷹はとても賢いことや、その足で獲物を「つかみ取る」ということから、賢く運気をつかみ取るという意味もあるようです。
茄子
なんでいきなり茄子?と不思議に思いますが、茄子は花が咲くと必ずと言っていいほど実がなるので、子孫繁栄やたくさん実を結ぶという意味があるようです。
「茄子」を「成す」にかけて、財を成すや子を成す、事を成すと縁起がいいとされています。
扇
古くから扇は、儀式や踊りを舞う時に使用する小道具として使われてきました。お祝い事やお祭りなどの人が集まる際に、なくてはならないものでした。人が集い、末広がりでめでたい事にあやかり吉夢とされたそうです。
煙草
煙草はお酒とともに、お祝い事やお祭りなど、人々が集う席には欠かせないものです。雰囲気を盛り上げ、人々を和ませるからです。また、煙草の煙は、上に上にとぐんぐん上がっていくことから、運気上昇の意味もあるそうです。
座頭
座頭とは髪の毛を剃った盲人のことを言い、「毛が無い」ことから「怪我が無い」とされ、家内安全を願う意味があるそうです。
ちなみに、1富士2鷹3茄子と4扇5煙草6座頭の6つの言葉は互いに対応する意味をもっているそうです。「富士」と「扇」は、形が末広がりで子孫繁栄や商売繁盛、立身出世を意味しています。
「鷹」と「煙草の煙」はぐんぐん上昇して行くことから運気上昇を、「茄子」と「座頭」は両方とも「毛が無い」ことから「怪我が無い」と家内安全を意味しています。
他にもあった続きとは?
さらに、「四葬礼(よんそうれい)五雪隠(ごせっちん)」という、これまた難解な言葉があります。葬礼とは葬式、雪隠とはトイレのことです。葬式とトイレの夢って、あまり見たい気はしないですよね。
でも、これは逆夢と言われ縁起がいいとも言われているのです。過去の嫌なことが消えてしまうとか、身の回りにいい変化が起こることの予兆と言われています。
さらに、トイレは金運ととても関係が強いようです。金運が良くなるのなら、今度の初夢は是非、トイレの夢が見たいと思ってきませんか?
初夢っていつ見る夢なの?

ところで初夢とはいったい、いつ見る夢のことを言うのでしょうか?これにも諸説あって、人によっては、日が違う場合があります。
「元日の夜に見る夢」や「2日の夜に見る夢」と思っている人が多いのではないでしょうか。
江戸時代では、大晦日の夜から元日の朝にかけて見る夢、正月元日の夜に見る夢、正月2日の夜に見る夢と諸説あり、時代の移り変わりとともに、日にちも変わったようです。
31日の夜は、お正月準備や除夜の鐘などで忙しく、寝る時間が少ないため元日の夜になり、その時代は仕事始めが2日だったために1日の夜はせわしない、いい夢ならゆっくり見たいものだと2日の夜になったとか。
また、いい初夢を見られるという宝船の絵を売りにくるのが、仕事始めの2日だったため、だんだんと初夢も2日の夜になったという話もあります。
今でも、大みそかの夜は紅白を見たり、カウントダウンをしたり、元日も初日の出や初詣に出かけたりで、あまり寝ない人が多いのではないでしょうか。
確かに、ゆっくり良い夢をみようとなると2日の夜なのかもしれませんね。めでたいお正月ですから、元日から3日までに見た夢で、一番いい夢をその年の初夢と考えていいのではないでしょうか。
まとめ
縁起の良い初夢とされる、「一富士二鷹三茄子」は、諸説ありますが、戦国武将「徳川家康」に由来しているという説が多くあります。
「己を責めても人を責めるな」と、人の上にたちながらも決して慢心せず、264年も続く天下泰平な江戸幕府を開府した、徳川家康にかけて縁起が良いとされた初夢ベスト3。
実はベスト6まであり「四扇、五煙草、六座頭」という続きがありました。これらは開運や立身出世、家内安全といったこれからの1年の運気上昇を意味するものです。
また「不死」や「成す」「怪我無い」などの掛け言葉で、運気を引き寄せる意味もあります。夢は自分自身が気づいていない、心の奥の想いを知らせてくれたり、未来をもっと良くするための、メッセージでもあると思います。
良い夢であればそれを信じて前進し、今年1年を幸運の年にしてください。悪い夢であれば夢の意味を参考に、1年を前向きに進んで幸運を呼び込み、より良い年にしてほしいと思います。
江戸時代には、吉夢を見ることができると、七福神の乗った宝船を描いた「宝絵」がとても売れたそうです。「宝絵」を枕の下に入れて、良い初夢を引き寄せてみてはいかがですか。
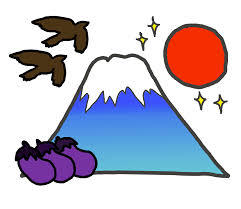




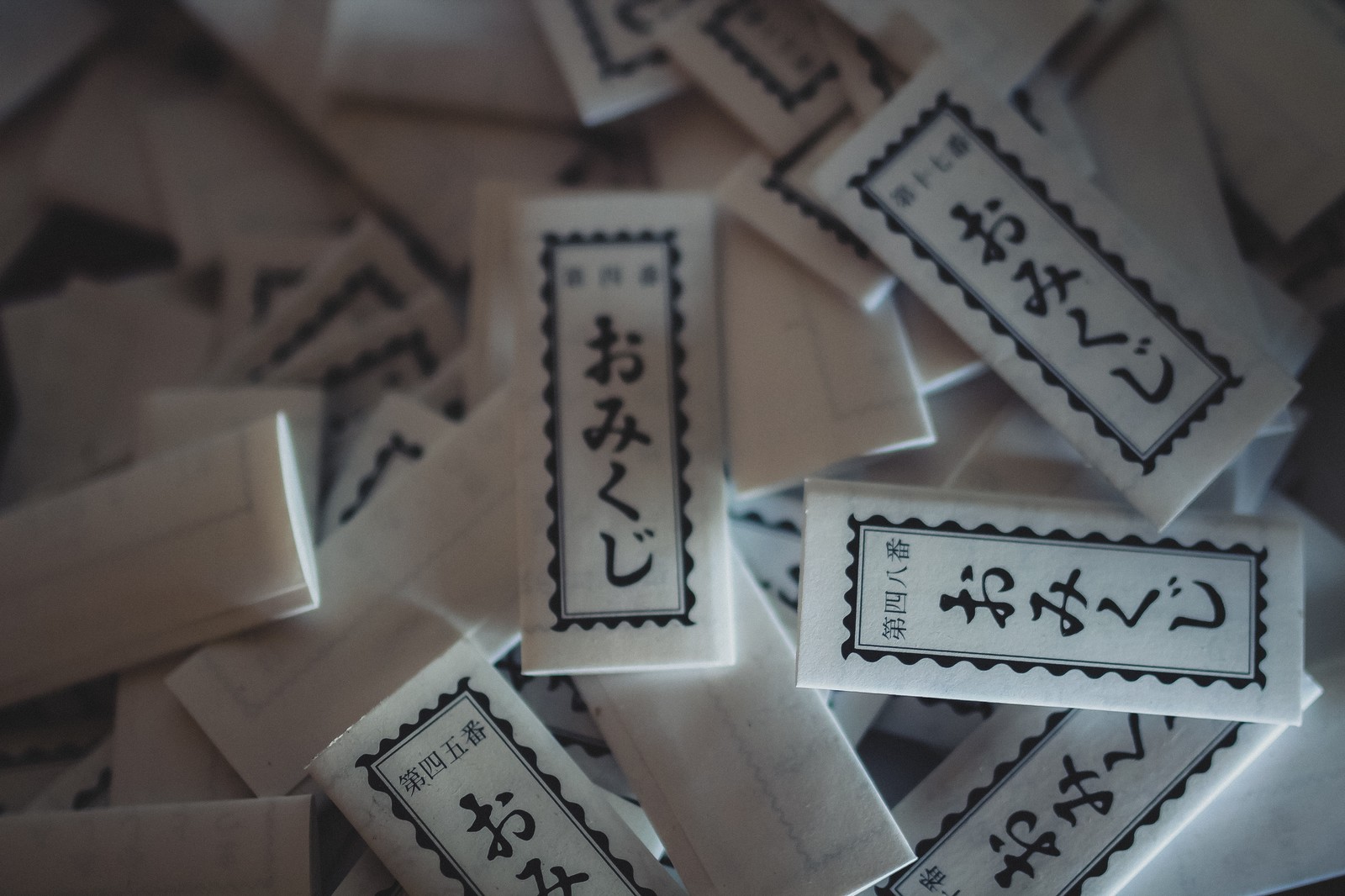










コメントを残す