突然ですが、皆さんは母の日や父の日にプレゼントを贈っていますか?
私は自分の両親には一切何も贈りません。
しかし、結婚して義父母と同居するようになってから、夫の兄弟が毎年ギフトを送ってくるのにびっくり。
確かに同居する義父母は優しい方で、毎日のようにお世話になっているので数年前から義父母にだけは贈り物をするようになりました。
相変わらず実家には何もしていないのですが、何もしないのは良くないのでしょうか。
気になって調べてみると、何もしない人も少数ながらいることが分かってきました。
また、贈っているけれど止めたい、という方も。
母の日、父の日に何もしないのは良くないのか、また途中で止めることの是非を考えていきたいと思います。
母の日、父の日はいつどこで始まったの。
まずはじめに確認しておきたいのは、母の日、父の日の起源です。
なぜそういうお祝いがされているのか分からないのに、贈り物をする意味などないと思うからです。
母の日の始まり

母の日を作ったのはアメリカ人のアンナ・ジャービスという女性です。 アンナは母親を大変に愛しており、母が亡くなった2年後、1907年の母の命日に教会で「母の日」を祝う会を開きました。
母の日の習慣はそれから少しずつ広がっていきました。初めて開かれた会が5月の第2日曜日だったことから、そのまま5月の第2日曜日は母の日とされるようになりました。
1914年にはアメリカの正式な国民の祝日になりました。ずいぶん早く全米に普及したのですね。
父の日の始まり

父の日も、母の日と同じくアメリカで生まれました。
父の日が生まれたのは1909年。 ソナラ・ドットという女性が、母の日があるならば父の日も作るべきだと考えたのが始まりです。
ソナラは母親の死後、自分と兄弟を男手一つで育ててくれた父親を敬愛していました。
ソナラも教会で父の日を祝ってもらいました。彼女は父親の誕生日にちなみ、6月の第3日曜日に父の日のお祝いをしました。
国民の祝日として正式に定められたのは1972年。
母の日と比べるとずいぶん遅くなったのが興味深いところですね。
どちらも、相手を愛する気持ちから自然と始まったようです。
これは私の推測ですが、二人の思いに共感した人が大勢いたからこそ広まっていったのでしょう。
親に感謝する気持ち、がポイントなのだと思います。
母の日、父の日に何もしたくない4つの理由

まくら株式会社が運営する「母の日.me」によると、母の日に特に何もしない人は約13%、父の日に特に何もしない人は約24.5%いるようです。
特に何もしない人はどういう考えで何もしないのでしょうか。
理由1:お金がない
理由の1つ目はお金が無いこと。
贈りたい気持ちは持っているけれど、金銭的に厳しい状況にあった場合、自分や子供を優先するのは当然のことです。
ギフトは贈らずに言葉で気持ちを伝える人もいるようですが、一般的なイメージとしてはカーネーションを贈るなどというのがありますので、贈れないならいっそのこと何もしないという結論に達するのかも知れませんね。
理由2:習慣、興味がない
元々こういうイベントに興味がない人も一定数います。
私もそうなのですが、私の両親は母の日、父の日のみならず結婚記念日も一切お祝いしていませんでした。
そういう家で育ちましたので私も結婚記念日に夫婦で食事をする等という習慣に、本当に驚きました。
もちろん母の日や父の日に祖父母に贈り物をしている姿を見たこともありません。
悪気もないのですが、そもそも自分に関係あるイベントだと思っていないので、祝うという発想が湧いてこないのです。
理由3:他の記念日とまとめている
親の誕生日や結婚記念日が母の日や父の日と近い場合は、まとめてお祝いという形にしてどれかを省略する人もいるようです。
5月は結婚式の多い時期でもありますので結婚記念日のお祝いとしてまとめてしまうと1回で済んで正直楽です。
母の日、父の日の由来も命日や誕生日でしたので、誕生日をお祝いしておいたらそれで良いと考えることもできそうですね。
理由4:親に対してマイナスの感情がある
過去に親との関わりで良くない思い出があると、親に対してマイナスの感情を抱いてしまいます。
幼い頃に辛い仕打ちを受けた。自分の誕生日や受験の合格などを祝ってもらえなかった。兄弟で差別された、など人それぞれ事情はあるものです。
過去に贈ったけど喜ばれなかったり、粗末に扱われた経験もマイナスの感情に繋がります。
元々が母や父への愛情や感謝から生まれた行事ですので、そういった感情がなければ贈り物をしようとは思わないことでしょう。
また義父母に対しては、自分の親でないのだから配偶者がやるべきだと考える人もいます。結婚を反対されたり、訪ねた時に辛く当たられたのが尾を引く場合もあるようです。
母の日、父の日に何もしなくてもいいの?

母の日、父の日の贈り物は義務ではありません。何もしなかったからといって問題が起こるわけではありません。
何もしなくていいか不安になる人は、結局のところ周りの人からどう思われるか、相手から責められるのではないかと不安に感じているのではないでしょうか。
先ほど見てきた通り、母の日も父の日も感謝する気持ちから生まれた風習です。
相手に対して心から感謝する気持ちがないのでしたら無理に贈り物をすることはないと思います。
また、元々アメリカの風習であったものがここまで日本に広がったのは、ギフトという形でたくさん買い物をしてほしい、と言う売り手側の戦略であることも見逃すことはできません。
結局のところは自分がどうしたいかを決断するしかないのではないでしょうか。
今まで贈り物をしていたけどやめたい場合は

これまで父の日母の日を祝っていた方の中にも、これまでしていた贈り物を止めたい方は多いのではないでしょうか。
私は個人的には止めても問題ないと思っています。
止める理由は、相手に言っても言わなくてもどちらでも良いと思います。
聞かれた場合は、変に言い訳せずにはっきりと正直な理由を言ってしまっても良いでしょう。
経済的理由でしたら仕方がありませんし、感情的な理由で、伝えたら相手の気分を害する可能性がある場合でも正直に言っていいと思います。
なぜなら、実の両親にしろ義父母にしろ、贈り物を辞めたいと思っている時点で既に相手の方との関係はあまり良くないと考えられるからです。
そのご縁が切れてしまったからといって、この先困るでしょうか。
そこを考えてみて、スッキリすると思えるのであれば人間関係も整理していけば良いのです。
まとめ

母の日や父の日に贈り物をしないことは良くないことなのでしょうか。
これまで贈ってきた習慣をやめても問題はないのでしょうか。
母の日も父の日も元々は相手に感謝する気持ちから生まれた行事です。
アメリカでは正式な国民の祝日ですが、元々日本の行事ではありません。
今は日本でも定番の行事となりましたが、母の日に特に何もしない人は13%ほど、父の日に特に何もしない人は24.5%ほどもいます。
何もしない人にも様々な理由がありますが、元々義務でもありませんし何かを送るかどうかは結局のところ自分で決断するしかありません。
今までしてきた贈り物を止めたい人も同じで、自分の判断で止めたいのなら止めてしまって問題はないでしょう。
贈り物をやめることで相手の気分を害することもあるかもしれませんが、その場合は人間関係も整理すれば良いのではないでしょうか。
贈り物をするのか、何もしないのか、メッセージだけ伝えるのか。様々なやり方がありますが、結局のところ贈り物は気持ち次第。
自分の心が一番幸せになる方法を選んでいけば良いと思いますよ。






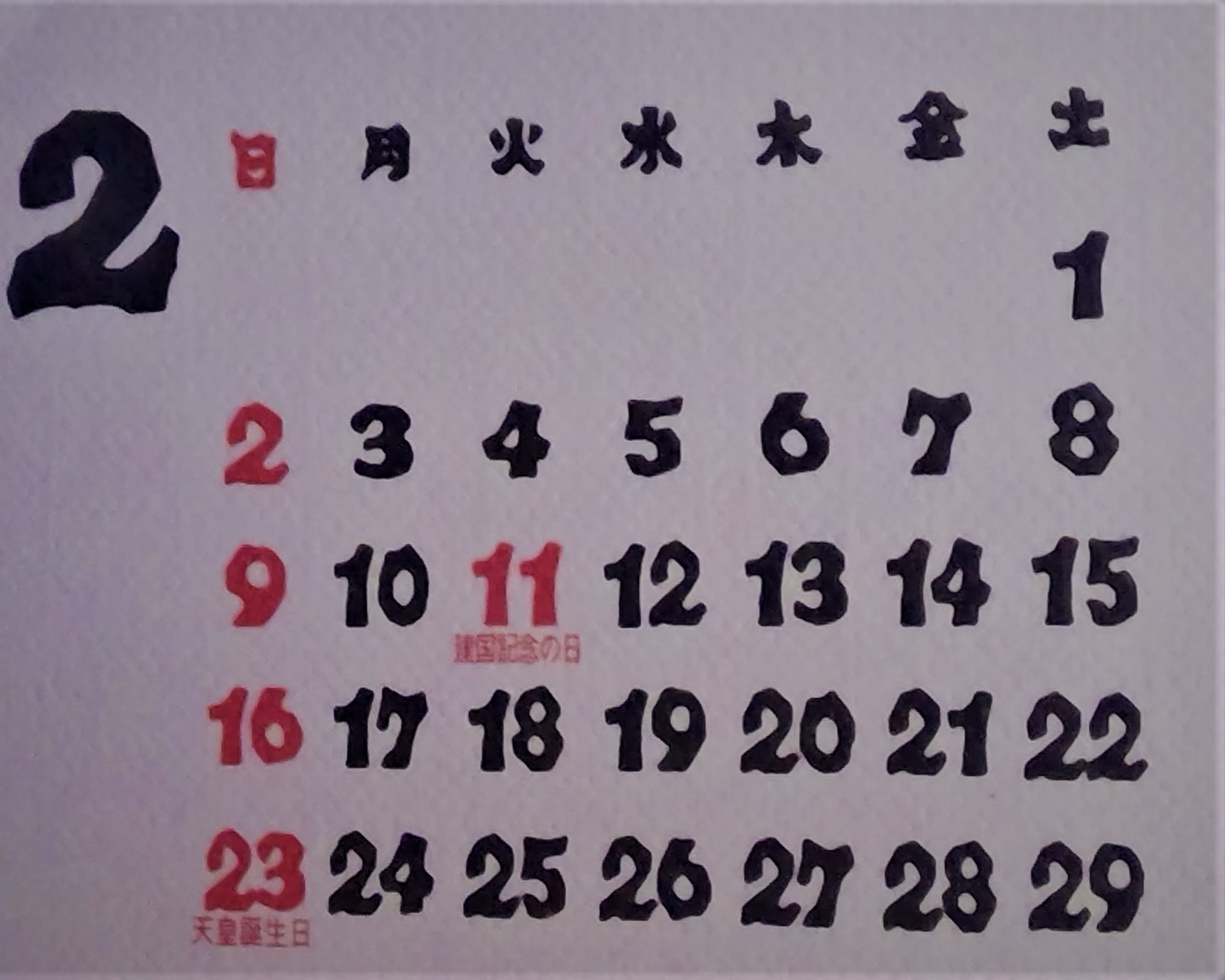




コメントを残す