「ほらほら、寒いからおこたに入りなさい」
「おこたでねんねしてたら風邪引くよ」
寒い季節がやってくると、そんな言葉を昔、母親からかけられたのを懐かしく思い出します。
何でしょう、「お」を付けただけなのに、こんなにやわらかい印象を与えることができる。日本語って奥深いと思いませんか。
しかし、あることに気付いたんです。この「おこた」という言い回し、母親や祖母から聞いたことはあっても、父親や祖父からは聞いたことないということを。
父親からの言葉ですと、「こたつで寝るな。風邪引くぞ」という感じでしょうか。
同じように、私も娘に対しては「こたつ」と「おこた」の両方を使っていますが、主人はいくら幼い子どもに対してとは言え、「おこた」とは言いません。
実際に主人に「おこた」という言葉を使うかと質問すると、「使わない」と言う答えが返ってきました。
では、私が和歌山県出身で、主人が大阪府の南の方の出身ということで、地域差なのかな?と考えましたが、同じ大阪の南の方の出身の義母は、「おこた」と普通に使います。
「おこた」というのは方言なのかなと思っていましたが、これはどうやら違うようです。
では一体、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
「おこた」は方言ではない
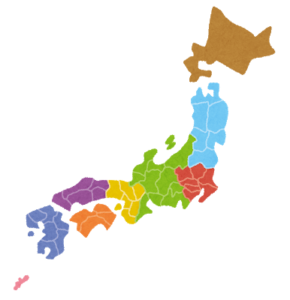
私の両親、祖父母共に和歌山県の出身、主人の両親ともに大阪府の南の方の出身ということだけでは、方言ではないと断定するには難しいと思ったので、調べてみました。
ネット上で検索して引っかかったものだけを拾い出してみると、以下の都道府県や地域では普通にこたつのことを「おこた」と呼ぶそうです。
東北、北陸地方、東京、信州・木曽地方、長野県、名古屋、京都、徳島、高知(年配の方)など
この答えを見てみただけでも、日本全国に「おこた」といういい方は散らばっているのが分かります。(イントネーションの違いなどは考えない)
方言ではないとすると、どうして「こたつ」のことを「おこた」という言い方があるのでしょうか。
「おこた」は女房言葉である

方言ではなさそうだということは、では一体何の言葉なのか、と辞書を調べてみました。
「おこた」とは
コタツのこと。 丁寧の「お」を付けて「こたつ」自体は略した表現。 「おこた」のような、丁寧の「お」と省略の要素を含む語は、女房言葉と呼ばれる。 他の例に「おなら」などがある。
実用日本語表現辞典
例えば「パーソナルコンピューター」のように長い物の名前を「パソコン」のように略す日本語には理解ができますが、「こたつ」と言ったような短い物の名前が略されているということもあるというのです。
つまり「こたつ」が「こた」と略され、それに「お」がついて「おこた」になったわけです。
イランの暖房器具「コルシ」…(略)…
現在の「こたつ」の漢字表記は「炬燵」が主流であるが、室町時代には「火闥」「火踏」「火燵」、江戸時代には「火燵」「巨燵」などと表記された。なお、燵は国字である。語源としては「火榻」に由来するという説がある。また略称として「こた」があるがあまり用いられない。しかし、丁寧語の「お」をつけた「おこた」という言い方は多く女性に用いられている。ウィキペディア
「女房言葉」とは

御所言葉とも言われますし、女房詞とも表記されます。室町時代初期頃から宮中や院に仕える女房と呼ばれる女性たちが使い始め、時代を経ると庶民も使うようになったものです。
※女房…平安時代から江戸時代までの貴族社会の中で、朝廷や貴顕の人々に仕えた奥向きの女性使用人のこと。主人の身辺に直接関わる雑務をこなす身分の高い使用人で、乳母や家庭教師、秘書などの役割を果たした人々。
そしてその一部は現在でも用いられています。
語の頭に「お」を付け、丁寧さを表現するものがあったり、語の最後に「もじ」を付けて遠回しに表現するものなどがあります。
現代でもよくつかわれる女房言葉の例
- 語頭に「お」を付けたもの
| ことば | 成り立ちや意味 |
| おかず | 主菜と共に出される惣菜は数々取り揃えるものであるということから。 |
| おから | 大豆から豆乳を絞った後の残りかす。搾りかすのことを「から」と呼んでいたことから。 |
| おひや | 「お冷やし」と言っていたものが略された。お冷。冷水のこと。 |
| おむすび | 女房達が使っていた言葉「おむす」から「おむすび」となる。握り飯。 |
| おでん | 田楽豆腐を略して「お」を付けた。 |
| おこわ | 「強飯(こわいい)」からくる。ご飯が固い=こわい と言う。 |
| おじや | 雑炊。「じや」というのは「じやじや」と煮える音から。 |
| おはぎ | 周りにまぶされた粉餡が萩の花が咲き乱れた様子に似ていることから。 |
| おいしい | もとは味がよいという意の女房詞で「いしい」に接頭語の「お」が付いたもの。 |
以上のように、圧倒的に食に関する女房言葉が多い。また、以下のような例もあります。
| ことば | 成り立ちや意味 |
| おつむ | 頭を意味する「つむり」という語から。 |
| おなら | 「お鳴らし」と言っていたものから。 |
「屁」と言ってしまうことはさすがにそのまますぎるというのは、今の私たちでも感じます。
それを「鳴るもの」=「お鳴らし」と表現し、「し」を脱落させたことで、とてもかわいらしい印象になりました。
- 語尾に「もじ」を付けたもの
| ことば | 成り立ちや意味 |
| しゃもじ | もともとは「杓子(しゃくし)」の語頭の「しゃ」に「もじ」を付けた。 |
| ひもじい | 「空腹である」という意味の「ひだるい」の「ひ」に「もじ」を付けた。 |
なぜそのような言い回しをしたのか
宮中では、食べるものや着るものの名前をそのままの名前で呼ばないことになっていました。
女房達は身分の高い使用人たちであったため、物の名前をそのままあからさまに言葉に出すということは、「はしたない」とされていたようです。
ですので、宮中では特に彼女たちの日ごろ身のまわりにあったものに対して、女房言葉を使っていました。衣食に関するものが多いのはそのためでしょう。
こうして女房言葉というものを見てみると、確かに物事をそのまま名前で呼ぶよりも、優しい印象を受けるような気がしますね。
そして実際、以下のような効果もあったようです。
女房言葉の効果
- 上品で優雅に聞こえる
宮中にいた身分の高い女房によって作られたものですから、そのことばづかいは、上品で優雅な印象を受けます。
- 女らしさが見られる
「女房言葉」は女房たちが生み出したものです。当然、彼女たちは女性です。女性から生まれた言葉なので、「女房言葉」には女性らしさが感じられます。
表に上げた一部の例は、現代は男女ともによく使う言葉ではありますが、「おこた」という女房言葉を考えると、男性よりも女性の方がよく使っている印象があります。
- 遠回しなことばづかいで、多くの場合「隠語」の性格を持つ
隠語というのは、仲間内だけで通じる言葉や言い回しや専門用語のことで、外に秘密がもれないようにしたり、仲間意識を高めるために使われる言葉のことです。
女房たちというのは、宮中や院の中で生活をしていた使用人たちです。彼女たちにしか知らないこともたくさんあったでしょう。
時には自分たち以外の人には知られたくないこともあったでしょう。そう言った時に、彼女たちが作り出した女房言葉というのは、隠語の役割も果たしていたのかもしれませんね。
例えば、「あのお方はおつむがよろしくないですわね、おほほほ」などと、話していたのでしょうか…。
- シャレた言いまわしになる
女房たちも時には気を抜いて、シャレを言ったりして楽しんでいたのかもしれませんね。
まとめ
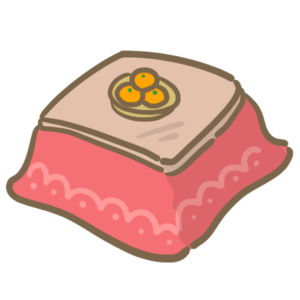
- 「こたつ」と「おこた」は同じ物体を指し、方言ではない。
- 「おこた」は女性特有の女房言葉と言われるものである。
- 女房言葉とは、室町時代初期頃から宮中や院に仕える女房たちが使っていた特有の言葉である。
- 女房言葉は身近な衣食に関する言葉が多く、現代もなお使われているものがある
- 女房言葉には、優雅さや上品さ、優しさと言った印象がある。
言葉を調べていると、日本語がいかに奥深く、美しいのかということに気付かされます。
これは余談ですが、私たちが子供のころから親しんでいた「こたつ」、今の子どもたちは知らない子もいるんですよね。
「おこた欲しいなあ」とつぶやいた私に、娘が「おこたって何?」と返した来たときの衝撃は忘れられません。
私の実家には昔こたつがありましたが、リフォームしてからはもっぱら床暖房の生活。義理の実家にまだこたつがあるので、それを初めて見たときの娘の第一声は「テーブルに布団がある!」でした。
生活が便利になっていくのと共に、昔から使っていた物がなくなりそれを示す言葉も使われなくなっていく。
そのような言葉の消えていくまさにその場面に私たちはいるのかもしれません。
















コメントを残す