今日も1日お疲れさまでした。翌日の準備も終了。電気を消して布団にもぐり、さあ就寝。
…というときに何故か突然考え事が止まらなくなり、考え事のループにはまってしまうことはありませんか?
考えないように意識すればするほど思い出して、翌日に支障が出るのではないかと不安になります。
眠れないという不安がさらに不安を呼び、気づいたときには小鳥のさえずりが朝を知らせてくることも…。
就寝前は疲れているのだから考え事はやめたいのに、何故かやめられなくて本当に困ってしまいますね。
どうして人は、寝る前に考え事をしてしまうのでしょうか?
寝る前の考え事がやめられないのはなぜ?

人間が自分でコントロールできるのは、意識的な思考の一部だけといわれており、膨大な思考のほとんどは潜在意識の中にあります。
あなたの脳は睡眠中に、1日の活動中に起こった出来事を整理しようと試みます。実は膨大な量の情報が溢れて、大渋滞を引き起こしている状態です。
日中はさほど気にならないのに夜眠る前に潜在意識の中から、まるでスポットライトを当てたかのように浮かび上がります。
脳内の情報過多による混乱が睡眠を妨げてしまうのです。
心地の良い寝つきを邪魔する原因はさまざまです。まずは睡眠の仕組みから見ていきましょう。
睡眠のメカニズム
人間の睡眠は2種類の睡眠によって支えられています。レム睡眠とノンレム睡眠によって、疲れた脳と体を休ませて回復させているのです。
入眠後は、ノンレム睡眠が次第に深くなります。そして深い睡眠が続いた後に、レム睡眠へと移行します。
これが健康な人の睡眠サイクルで、おおよそ90分~120分間隔で繰り返されています。
レム睡眠
前身の筋肉は緩んでいますが、脳はアクティブに動いており夢を見ている状態で、起きていた時の記憶の整理が行われています。
呼吸は浅くなり、心拍数や呼吸が不規則になります。
ノンレム睡眠
いわゆるスイッチオフの状態です。脳も体も休んでいますが、ある程度の筋肉は働いています。
心拍数や呼吸の回数は安定しているため、ゆったりとした呼吸になります。
体内時計
人間には1日周期でリズムを刻んでいる体内時計が備わっています。個人差はありますが、体内時計の周期は24時間より少し長いといわれています。
体内時計は夜になると眠くなる働きを持っており、毎朝日光を浴びることでリセットされています。
睡眠ホルモン
良質な睡眠に欠かせない3つのホルモンについてお話します。
セロトニン
セロトニンは幸せホルモンとも呼ばれています。セロトニンがたくさん分泌されていると心は穏やかになり、明るくなれるものです。
日光を浴びることで分泌されやすくなりますが、夜は日光がありませんのでセロトニンの分泌が抑えられてしまうと考えられています。
メラトニン
メラトニンは睡眠ホルモンとも呼ばれています。セロトニンを原料につくられ、夜間に分泌が増加します。
睡眠の質を向上し安定させ、体内時計の修正をするなど睡眠と覚醒のリズムを調節する役割を果たしています。
コルチゾール
コルチゾールは夜から朝にかけて分泌が増加し、目覚めの準備を促す役割を担っています。
一方でストレスホルモンとも呼ばれており、ストレスを受けたときに脳からの刺激により分泌が増え、自律神経系や内分泌系に影響します。
心地の良い入眠に辿りつくには

人によって悩みはさまざま。実は「これをしなければいけない」という特定の対処法はありません。対処法もさまざまなのです。
だからこそ、自分にぴったりの対処法を探してみましょう。
何に悩んでいるのか明確にする
脳内で溢れているたくさんの情報を、一旦整理する必要があります。どんな方法を取ればいいのか見ていきましょう。
思うがままに書き出す
その日の出来事をはじめ、日頃感じていることを日記やノートなどに書き出します。言葉を選んだり、まとめようとせずに思うままに筆を走らせてください。
書き出すことで「何に」「どんな風に」悩んでいるのか整理することができます。
考え終わったら心を無にしてゆっくりと深呼吸しましょう。就寝前には頭も心も穏やかな状態にして休ませることが必要です。
考え事を人に話す
情報過多により脳が働いていることが心地よい入眠を妨げているのだとしたら、話を聞いてもらうことで情報が整理されます。
自分だけで解決できない悩みは、誰かにそっと打ち明けてみましょう。
しっかり悩みに向き合う時間を作る
落ち込むときは時間を決めてたっぷりと落ち込みましょう。
たとえば失恋した時。バッドエンドの映画を観たり、失恋ソングをひたすら聞いたりしてどっぷりと失恋に浸ることで不思議と気持ちがすっきりするものです。
自分の感情を押し殺さず、受け入れるための時間は必要です。それは明日を楽しく生きる糧となるでしょう。
新しい可能性に目を向ける
望んだ結果が時間や労力をかけてもなかなか手に入らないときは、思い切って別の可能性に目を向けることも重要です。
路線変更することで、新たな気づきや発見があり前に進めるかもしれません。
「あんなに時間をかけたのに…」
「あんなに頑張ったのに…」
そんな風に思ってすぐには踏み切れないかもしれません。
しかし、考えと行動を切り替えることで違った視点から改めて見直すことだってできるはずです。
就寝前の行動を儀式化する
人間は習慣の生き物です。関連付けてルーティン化することによって脳が行動を覚えていきます。
寝る前に毎晩繰り返すことで睡眠へ向けて準備する訓練になるのです。
ポジティブなことを思い出す
就寝前には、凝り固まった自分自身の心と体をほぐしてあげるために、ほんの少しでもポジティブなことを思い出してみましょう。
たとえば「今日のランチが美味しかった」「こんなことをして褒められた」など、1日の出来事の中から探してみると見つかりやすいかもしれませんね。
リラックスタイムを設ける
例をいくつか挙げてみます。自分に合ったリラックス方法を見つけてみましょう。
- 入浴する
- 音楽を聴く
- 本を読む
- ハーブティーを飲む
- キャンドルを灯す
- ペットと戯れる
リラックスタイムの際にカフェインやアルコールの摂取はなるべく控えましょう。一時的なリラックス効果は期待できますが、入眠を阻む原因になってしまいます。
日中に体を動かす
体内時計をリセットし、生活リズムにメリハリをつけるためにも、いつもより少しだけ早起きしてランニングやジョギングをおこなうのも効果的です。
また、日頃のストレス発散のために気持ちよく汗を流せるスポーツジムに通うのもいいですね。時間がとれないのであれば、ラジオ体操やストレッチだけでも十分です。
いっそのこと開き直る
睡眠時間が短くて不安になったとしても大丈夫。季節や年齢によっても、人によっても変わります。
少しくらい眠れなかったとしても、朝の目覚めがすっきりと爽快であり、日中の活動中にも支障がなければ十分な睡眠が確保できているということです。
長く眠れば健康になるわけではありません。長い睡眠時間を得るより、年齢や個人に応じた良質の睡眠をとることが重要です。
まとめ

ここまでをまとめてみましょう。
- 寝る前に考え事をしてしまうのは情報過多によるもの
- 考えごと・悩みを明確にし、解決までの道筋を立てる
- 寝る前の行動をルーティン化する
- 寝る前には心身ともにリラックスした状態にする
- 少しくらい睡眠時間が短い日があっても大丈夫
寝る前に考え事をして眠れなくなる夜は誰にだってあるものです。人間は、心のほんの一部しかコントロールできません。
悩みと上手に付き合うことで自分を大事にしてくださいね。あなたが明日、さわやかな朝を迎えられますように。
それでは、おやすみなさい。




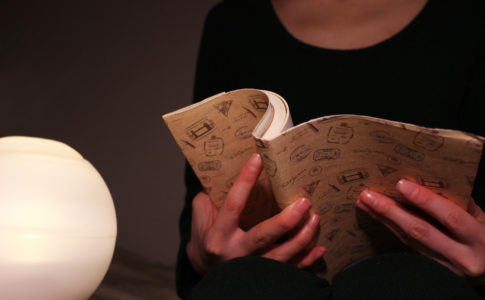











コメントを残す