秋から冬に季節が移り変わる頃。少しずつ空気のひんやり感が変わってきますね。
小学生の時は、頬にあたる冷たい風にも負けずに元気に登校していました。
「子供は風の子」なんて言われていた時期は、本当に元気でしたが、今は寒すぎて元気に外を歩くのは無理ですね(笑)
そんな時代から今も変わらず、寒くなってくるとできるものがあります。
それは草が生えているところや土が見えている所にある霜柱。
あのシャリっとした軽い氷の感触が何とも言えず。見かけると、よく踏みつけて遊んでいたのを思い出します。
そして雪とは一味違う感じで地面が真っ白になる霜。
子供ながらに、段々と冬が近づいているんだなと実感する出来事でした。
そんな霜柱や霜って実は仕組みが違うのをご存知ですか。
「そんなの同じく凍ったものなのでは」と思ったあなたには、ぜひ知ってほしい内容です。
霜柱や霜の仕組みや関係する言葉を知って、冬ならではの情景を楽しんでみませんか。
霜柱と霜の違い
凍る現象によって起こる霜柱と霜。どのような違いがあるのでしょうか。
霜柱とは
寒くなっていき温度が0℃以下になると、土の表面が凍ってきます。土の中が毛細管現象によって表面付近まで、どんどん水分を引き上げていきます。
表面が凍るほど気温が冷えているので、引き上げた水分も徐々に凍っていきます。結果、氷の柱=霜柱が出来上がるのです。
毛細管現象とはタオルを例に挙げると分かりやすいと思います。
タオルがもし網戸のように隙間があいている状態で作られているとしたら、テーブルにこぼした水をきちんと吸収してくれるでしょうか。
隙間がある状態だと、あまり吸収されずに残ってしまうと考えられます。
タオルは繊維がぎっしりとつまった状態なので水分を吸収し、それと同じ状態が土の中でも起こるのです。
霜とは
空気中の水蒸気が昇華して、氷の粒となりそれが植物や車の窓などにくっつくのが霜となります。
昇華という現象は学校の授業で習っていますが、覚えていますか。私は言葉までは知っていたものの、意味はよく理解できていませんでした。
あらためて調べてみると、昇華とは固体から液体にならずに固体から気体、または気体から固体になることです。
身近な例で挙げるとドライアイスです。
アイスなどを冷やすために入っているドライアイスですが、外に出していても白い煙が出ることはあっても、水にはなりませんよね。
地中の水分が凍ってできる霜柱と空気中の水蒸気が昇華してできる霜。
改めて考えてみると、2つの仕組みは全く違うことが分かりますね。ただ寒くなってくる時期にできることは共通しているようです。
他にも霜柱や霜ができる条件はあるのでしょうか。
霜柱ができる条件

霜柱ができる条件は3つあります。
- 地表の気温が0度以下
- 地中の温度は0度にならない程度
- 適度な水分と土の硬さ
地表の気温が0℃以下
気温は地面から1.5mほどの位置で計測しています。
今回地表の温度としたのは、地面付近は普段のニュースで発表されている気温より、低いためです。
もし気温が0℃の時だと、地表の温度はマイナスになってしまいます。
そうなると霜柱ができる次の条件に、当てはまらなくなります。
地中の温度は0℃にならない程度
気温がマイナスになってしまうと地中の温度も下がってしまいますよね。
地中がマイナスになってしまうと、中の水分が凍り始めてしまいます。
そうなってしまうと霜柱はできないのです。
適度な水分と土の硬さ
霜柱には適度な水分と土の硬さです。
さきほど霜柱は土の中の水分を引き上げると言いましたが、乾燥している土だと水分が引き上げられません。
反対に雨の次の日のように、水分を含みすぎているような状態も霜柱はできないのです。
また踏み固められたような場所だと、いくら適度な水分があっても持ち上げられないので、霜柱はできにくくなってしまいます。
霜ができる条件

霜ができる条件は4つあります。
- 放射冷却&晴れの天気
- 気温が4℃以下
- 風が弱いまたは無風
- 湿度
放射冷却&晴れの天気
放射冷却とは温かいものをそのままにしておくと、冷めていく現象のことです。例えば、お風呂のお湯。
使い終わった後に、ふたをしておけばお湯が冷めるのを防いでくれます。
しかし、冬の時期にふたをしないでそのままにしておくと、一気に冷めていきますよね。
同じことが天気にもあり、雲がない晴れた空だと昼間温められた熱がどんどん放射されて気温が下がるのです。
また雨が降るということは、霜柱や霜がおりません。もしできていても氷は水に溶けてしまいますよね。
気温が4℃以下
霜柱ができる条件でも少し触れましたが、気温は地面から1.5mのところで計測しています。位置が低くなれば、気温も下がり0℃ちかくになります。
ちなみに霜注意報が出るときの気温は、地域によって違いがありますが、最低気温が3℃~5℃くらいとなっています。
風が弱いまたは無風
風が強く吹いている状態だと、空気中にある水蒸気がかき混ぜられ、氷の粒が出来にくくなります。
湿度
湿度が低いと、空気中の水蒸気は吸収されてしまい、昇華できません。ある程度の湿度の高さが必要になってきます。
霜柱や霜ができる時期に注意したいこと

時期によって霜注意報が出ることがありますよね。農家や植物を育てている人は、注意が必要です。
寒さに弱い作物の場合、霜がつくと枯れてしまったり、霜柱ができると土が持ちあがることによって、根っこがむき出しになることもあります。
霜や霜柱ができる条件がそろっているなら、温かくするために布をかけたり送風機などを利用して、気温が低くならないように早めの対策をしておきましょう。
また車のフロントガラスに霜がつくと、なかなか取れなくて苦労しますよね。出勤前に大慌てなんて事態を引き起こすことも。
そうならないように、車のカバーや霜がつかないスプレーを準備しておくのも方法の1つです。
くれぐれも熱湯をかけて霜を溶かしてみようなんてことのないようにしてくださいね。
霜柱や霜に関する言葉
霜柱や霜に関する言葉はどういったものがあるのだろうと思い、いくつかまとめてみました。あなたが知っているものはありますか。
霜月(しもつき)
霜月は旧暦の11月の事を言い、現在の暦の別名としても使われているのですが、新暦と旧暦ではおよそ一か月ほどのズレがあり、2019年の旧暦11月は新暦の11月27日から始まります。
現在の暦は太陽暦といって太陽の動きに合わせたものとなっています。明治時代から使われ始めました。
明治以前は、太陽陰暦といって太陽の動きだけでなく、月の満ち欠けにも合わせて作られた暦です。旧暦ともいいます。
現在も沖縄の主な年中行事は旧暦で行われることがありますし、北海道の一部や宮城県仙台市では七夕が旧暦の七月七日で行われるので、馴染み深いという人もいますよね。
霜降(そうこう)
| 立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨 |
| 立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑 |
| 立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降 |
| 立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒 |
霜降は二十四節気の一つです。二十四節気は1年を24分割にし考えたもので、霜降の時期には地域によってですが、文字通り霜が降り始めます。
秋も終わりに近づき、徐々に気温が下がり始めるので、そろそろ冬の準備を始めたほうがいいという時期になります。
2019年の霜降は10月24日、2020年は10月23日と毎年異なりますので、カレンダーなどで確認してくださいね。
フロストフラワー
「フロスト」というのが、霜という意味でいわゆる【霜の花】。-15℃以下になる厳しい寒さになる北海道で、フロストフラワーが見られるというのです。
水蒸気の結晶が凍って、どんどん集まりきれいな花のようになりますが、たくさんのフロストフラワーを見るには条件があります。
- 湖の表面が凍る。ただし氷が厚すぎるのはダメ
- 氷の上に雪が積もっていない
- -15℃以下
- 放射冷却
- 無風状態
などです。
霜ができる条件と似ていますが、凍った湖の上に雪が積もっていないというのは、さらに厳しい条件に思えますね。
そうした条件が揃ったとき、フロストフラワーは見られるのですが、映像を見ただけでも本当に美しいと思いました。
フロストフラワーと北海道の美しさを感じる動画も併せてどうぞ。
シモバシラ
なぜカタカナ表記なのかと思った方もいると思いますが、実はシモバシラという名前の花があるからなのです。

白く可愛らしい花が咲いていますよね。見頃は9月下旬から10月上旬ですが、花だけでなく他の時期にも楽しませてくれるのです。それが冬の時期。
初冬の強く冷え込んだ朝、枯れた株元に地中から染み出した水分が凍って花のような美しい氷ができます。本物の花は秋に咲き、こちらも白い姿が清楚です。
引用 国営武蔵丘陵森林公園

真っ白い花のような氷ができていますよね。初めて見たときは、このような花が咲いているのかと勘違いしてしまうほどでした。
機会があれば、秋と冬の2度にわたって素敵な姿を見せてくれるシモバシラをぜひ見てくださいね。
まとめ
- 霜柱は土の地中にある水分が表面の氷を持ち上げながら凍っていく現象
- 霜は空気中の水蒸気が冷やされ、氷の粒となり植物や地面にくっつく現象
- 霜柱ができる条件は、晴れ・風が弱いまたは無風・気温が4℃以下・放射冷却
霜柱と霜は似ているようで、仕組みは全くの別ものでした。私は氷というだけで何となく同じだろうと思っていたので、びっくりでしたね。
気温が下がらないと霜柱が立ったり、霜が降りることはありません。
周りの人より一足早い冬の訪れをチェックして頂き、霜柱や霜が見られる頃にはもう本格的な冬が始まるんだなと実感してもらえたらと思います。




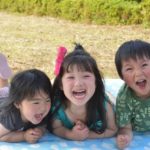




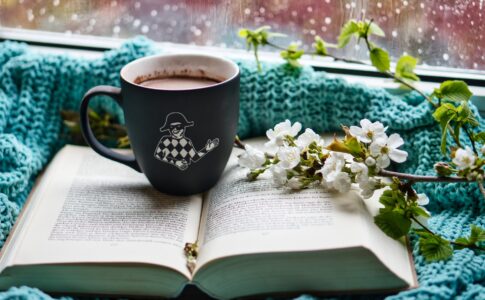







コメントを残す