「鬼はー外」「福はー内」と聞けば、節分ですね。
節分は煎った大豆(地域によっては落花生)をまいて、鬼をやっつけて、福を呼び込もうという日本に伝わる行事です。
また関西方面であったというその年の恵方を向いて海苔巻きを無言で食す恵方巻きも、だいぶ定着し、今や全国区となりました。
お正月が過ぎた時期くらいになると、恵方巻の宣伝があちこちであるくらいですよね。
実は節分にはもう一つ、福を招き入れるためにやることがあるのは知っていますか。
それは柊鰯(ひいらぎいわし)。
柊と鰯が、節分とどういう関係にあるのでしょうか。
ここでは柊鰯の作り方や片付けなど、とことん紹介していこうと思います。
まずはこの記事を読んでいるあなたから、私と一緒に学んでいきましょう。
そして次の世代にも伝えていきませんか。
柊鰯を作る準備をしよう

作る前に以下のものを準備してくださいね。
比較的、手に入れやすいものだと思います。
- 柊(鰯の頭を刺すので、枝が折れないようなものがいいですね。)
- 鰯1尾
柊鰯を毎年飾るような地域なら、スーパーでセット売りしているようです。
スーパーで柊の取り扱いがなければ、ホームセンターの花売り場などを探してみてくださいね。
ちなみに柊鰯に使用する柊は、クリスマスによく使われる赤い実のセイヨウヒイラギとは別のものなので、注意して下さいね。
生鰯を使用する場合は、傷みやすいので新鮮なものを選びましょう。
新鮮な鰯の選び方
|
生の鰯がなければ、丸干しされた鰯を使っても大丈夫ですよ。
準備ができたら、いよいよ作っていきます。
柊鰯を作る
- 鰯をグリルなどで焼きます。生のままでは使いません。
- 美味しく焼けたら、頭の部分を外します。胴体の部分はおかずにしましょう。
- 柊に鰯の頭を刺していきます。頭が上を向いている状態を作りたいので、エラから目に刺します。
これで出来上がりです。
思ったより簡単でしたね。鰯は必ず焼いてくださいね。なぜかと言えば、由来に関わってくるんです。
柊鰯の由来を先に知りたい方はこちらから
柊鰯の飾り方
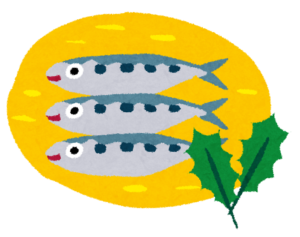
実際に作ってみたら、飾ってみましょう。柊鰯はどこに飾るのがいちばんいいのか決まっているのでしょうか。
また決まっている時期はあるか、お話ししていきますね。
いつ飾るのか
地域によって違うため、一概にこの日だとは言えませんが、小正月の翌日から節分の間に飾るのが良いということで、節分の日に飾ることが多いようです。
どこに飾るのがベストなのか
どこに飾るかといえば、ずばり玄関です。
玄関のドアに立てて置いたり、紐でつるすのもいいですね。
もし外に置けない場合は、玄関内に置くのも一つの方法ですよ。
家に飾りたいけど飾れない場合
玄関に飾るのは理解できたと思いますが、匂いが気になるなど飾ることができない場合もありますよね。
私が住んでいる地域は、節分の時期になると風が強いし、雪も降ります。
また集合住宅なので、なかなか飾ることもできません。
そんな事情がある方には以下の方法がおススメですよ。
折り紙の柊鰯
それは折り紙です。
これなら臭いもないし見た目が可愛いので、飾りやすいです。玄関が華やかになりそうですよ。
子供がいる方なら、由来を教えながら一緒に作ってもいいですよね。
また作ったものを壁面として飾っても、すてきだなと思います。
準備するものは、鰯を作る青い折り紙と柊を作るための緑の折り紙と組み立てるための割りばしとくっつけるためののりです。
特別な材料ではないので、準備しやすいですよね。
緑の折り紙は7.5㎝と小さめのサイズですが、15㎝サイズを四角形に折って1/4サイズになったものを切れば、オッケーです。
というわけで今回、私は上記のYouTubeを見ながら作ってみました。
それがこれです。どうでしょうか。

若干折り直しのあとが見えますが、思った以上に可愛くできたのではと、自画自賛してもいいですか(笑)
動画を見ながらすぐに出来ましたよ。
ぜひ作ってみてくださいね。
柊鰯の片付け方

無事に飾った柊鰯。この機会なので、片付ける時期や方法などもきちんと知っておきましょうね。
片付ける時期
飾る時期は地域によって違いますが、片付ける時期もそれぞれ違います。
節分の次の日に片付けるところが多いように思えますが、中には次の年の節分まで飾る場合もあるみたいですね。
おもしろいものになると、猫が鰯を食べるまでという地域もあるとか。
もし食べられなかったら、ずっと飾っているんでしょうか。
それもなんだかすごいですよね。
片付ける方法
そのままごみ箱に捨てるのも一つの方法ですが、飾ったものをそのまま捨てるのは、ちょっと気が引けるという人もいますよね。
そこでそのまま捨てる以外の片付け方を紹介したいと思います。
焚き上げてもらう
神社で焚き上げてもらったり、どんど焼きなどの祭りで一緒に焚き上げてもらう方法です。
ただ神社でも受け付けていない場所もあると思いますし、どんど焼きは節分より前の小正月の時期にあるので、すぐに処分したいという時には適していないかもしれません。
清めてから処分する
柊鰯に塩をまき、半紙などにくるんでごみに出す方法です。
この方法を使っている人も多く、また一番やりやすい方法だと思います。
塩はお清めに使われます。
感謝の気持ちをこめて、処分してくださいね。
柊鰯の由来

私は柊鰯を実際に見たことはなく、初めて知りました。
知らない人がみると、なかなか強烈な印象だなと感じます。
節分の時期に柊鰯がかかせないものになってきたのは、どういう由来があるのでしょうか。
昔からの言い伝え
昔から良くないことが起こるのは、鬼の仕業だと言われてきました。
その鬼を退治するには臭い(におい)のくさいや尖ったものが、魔除けになると信じられてきたのです。
なので、鰯を焼いたときにでる煙の臭いと柊の尖った葉は、倍増の効果があると考えられたのではと思っています。
「煙で鬼を寄せ付けないようにし、柊の葉で鬼の目を突く」と言われています。
改めて見てみると、鬼にやられてたまるか、やっつけてやるという強い決意が伝わってきますよね。
こういう経緯から、柊の別名は【鬼の目突き】と呼ばれるそうです。
作り方のところで、「必ず焼いてくださいね」と伝えたのは、鰯を焼いたときにでる煙も、柊鰯を飾るという意味では、大切な役割だからなんですよね。
なぜ柊鰯を玄関に飾るのか
柊鰯を玄関先に飾るのは、柊鰯が門守(かどもり)といって、門=家を守る役割だからです。
やっぱり厄介なものは家に入れたくないので、鬼を門前払いをしたんですね。
平安時代には柊鰯の風習はあったとされ、当時はボラを使用していたという記録もある様ですが、いつから鰯が使われるようになったかは分かっていません。
柊鰯が由来となったことわざ
柊鰯の由来にちなんで、ことわざを一つ紹介しますね。
それが【鰯の頭も信心から(いわしのあたまもしんじんから)】ということわざ。
これは柊鰯の風習からできたことわざで、鰯の頭のようなものでも信じる人にとっては、とても価値があるものという意味です。
実際の使い方としては、皮肉交じりに使うことがあるようですね。
まとめ
- 柊は枝つきのもを、生の鰯は新鮮なものを準備する。
- 鰯は焼く。
- 柊は鬼の目を突き、鰯を焼くときにでる煙は鬼を近寄せないと言われている。
- 玄関に飾る。飾れない場合は折り紙で代用してみる。
- 飾る時期や片付ける場所は地域によってさまざま。
地域によってはなじみ深い柊鰯。
今回初めて知った風習ですが次の世代にも知ってもらって、つなげていけたらいいなと思います。
私も節分の時期が近づく前に探してみて、なければ折り紙で作った柊鰯を飾ってみます。
あなたも節分には豆まきと柊鰯で鬼を追い払って、さらなる福を招き入れてみませんか。








コメントを残す